「引用」「転載」「出典」の違い【知っておくべき著作権の知識】

おゆきさん!
「引用」「転載」「出典」の違いって何ですか?
著作権が関係しているとは思うんですが、、、
詳しく教えてください。
ブログを書いていると「引用」は頻繁に行うことになります。
対して、「転載」を行うということは稀になるかと思いますが、引用との違いを理解しておくことは重要です。
そして引用するにせよ転載するにせよ、出典を明記しなければなりません。
今回は、「引用」「転載」「出典」の定義やそれぞれの違い、適切な方法、「著作権」などサイトの運営者として必ず知っておくべき著作者の権利について解説します。
適切な引用を理解しておくことで、何かを論じる時の根拠の裏付けとして強い味方になってくれるので、是非最後まで読んでみてください。
「引用」「転載」「出典」とは?
まずは、「引用」「転載」「出典」とはそもそも何かというところを簡単にさらっておきましょう。
引用と転載は、どちらも他人のコンテンツの一部、または全部を使用する行為自体を指します。
出典は、引用または転載したコンテンツ(引用元・転載元)のことを指します。
引用と転載との違いは、自分が作るコンテンツに「自分が創作した部分がどれだけ含まれているか」によります。
明確な基準がないので判別が難しいですが、コンテンツ全体を見た時に、自分の創作部分がメインなら引用、出典の部分がメインなら転載という解釈です。
「引用」「転載」「出典」を明記する理由
「引用」「転載」「出典」を明記する理由は、その元となる著作物を創作した「著作者」の権利を守るためです。
著作者の権利とは、著作者の著作物にまつわる正当な権利で、「著作権法」という法律によってこの権利は保護されています。
著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されており、代表的な例を挙げると、小説、エッセイ、曲、歌詞、絵画、風景写真、イラストなどで、コピーコンテンツではないオリジナルのものを指します。
このような著作物は、それを創作した人(著作者)に正当な権利があるとし、著作権法において、第三者の著作物の利用に関しての定義がされており、原則として著作者の許可が必要となっています。
「引用」「転載」「出典」は、他者の著作物を、その著作者の権利を侵害することなく自分のコンテンツで使用するために明記が必要となります。
引用にせよ、転載にせよ、それが他者の著作物であることを明示し、出典を明記して元となる著作物を示すことで、著作物とその著作者の権利を守ります。
WebコンテンツのSEOにおいては、エビデンス(根拠)を示して自身のコンテンツの信頼性を示すことの重要度が増しています。
そのため、今後も「引用」「転載」「出典」は頻繁に用いる必要があるでしょう。
トラブルに備えて著作物の正しい取扱いの知識を持っておいてください。
「引用」の定義と条件
まずは「引用」から、その定義と、適切に行うためのルールを見ていきましょう。
ここでは下記の3項目について解説します。
- 引用の定義
- 引用する場合の条件
- よくある不適切な引用の例
それでは順番に見ていきましょう。
引用の定義
引用は、他の著作者の著作物の全部、または一部を、そのまま自分の創作物に用いることを指します。
引用は、著作者の著作権を守るために、一定の条件を満たす必要があり、Webサイトなどで用いる場合にも十分に注意しなくてはなりません。
引用は、著作権法で以下のように規定されています。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。
「著作権法第三十二条」
その引用が、「公正な慣行に合致するもの」かつ「目的上正当な範囲内」であれば、公表された著作物の引用はできるとされています。
この場合の著作者の許可は不要となります。
引用する場合の条件
前述の通り、適切に引用する場合には「公正な慣行に合致するもの」と「目的上正当な範囲内」という条件を満たしている必要があります。
しかし、この表現ではやや抽象的で、具体的にどうすれば良いかが分かりづらいかと思います。
ここでは適切な引用の条件を詳しく5つに分け、具体的な基準を解説します。
適切な引用の条件は下記の5つです。
- 引用する理由が明確にあること
- 引用部分が主ではないこと
- 引用部分が明確に区別されていること
- 出典が明記されていること
- 引用部分が改変されていないこと
順番に見ていきましょう。
引用する理由が明確にあること
自分のコンテンツを構成する上で、他者の著作物を引用する必然性が認められることが条件の1つです。
統計資料や研究結果などのデータを引用して、自分が論じていることの根拠とする場合や、例として提示する場合など、他者の著作物を引用する場合には明確かつ正当な理由がないといけません。
引用部分が主ではないこと
いくら引用に必然性があっても、引用部分がコンテンツのメインとして見なされる場合には、適切な引用とは認められません。
引用した内容が「主」となる場合、著作物の「無断転載」として扱われる可能性もあります。
これはただ引用部分以外の「量」を増やせば良いということでなく、 「質」がより重要となります。
引用部分は、あくまで自分の創作物の補完程度という立ち位置です。
引用部分が明確に区別されていること
ここまでの条件を満たしていても、引用部分が引用であることが一目で分からないものは、やはり著作者の権利の侵害にあたると考えられます。
引用部分が他者の著作物であることが明確になるよう、引用するのが文章であればカッコで区切ったり、フォントや文字色を変えたりして、可能な限り引用部分以外との区別ができるように施しましょう。
出典が明記されていること
出典は、元となる著作物自体のこと、つまり「引用元」を指します。
引用部分のごく近くに、見る人にわかりやすく明記することとされています。
引用が適切に行われていても、引用元が誰の何という著作物かが分からなければ、著作者はただの使われ損ですし、著作権が守られているとは言えませんね。
また、情報の出処を知りたいという人にとっても不親切です。
出典は必ず明記しましょう。
引用部分が改変されていないこと
著作物は著作者が時間と労力をかけて作り上げた創作物です。
引用する際に少しでも改変すると、著作権法で規定されている「著作者人格権」のうちの「同一性保持権」の侵害に繋がるとされています。
改変には、文章に含まれる句読点や文字の表記、改行位置なども含まれることに注意が必要です。
元の文章を「一言一句変えてはならない」と考えてください。
ただし、Web上で表記できない旧字体や異字体の漢字を常用漢字に置き換えるなどの例外もあるにはあります。
その場合でも、字体を変更したことは明記しておきましょう。
よくある不適切な引用の例
ここまで解説した条件をクリアしておらず、トラブルに発展しかねない不適切な引用は往々にして見かけます。
特によくある例は下記3つです。
- 出典(引用元)を明記していない
- 引用としながら引用部分を改変している
- 引用部分がメインになっている
著作権法の違反は、著作権侵害に対する刑事上の罰則はもちろん、損害賠償の請求や、不当利得の返還請求といった民事事件として訴えられる可能性もあります。
著作権法は著作者の正当な権利を守るルールです。
バレなければ良いなどとは絶対に考えず、著作者の立場に立ち、敬意を持ってその著作物を取り扱うようにしましょう。
「転載」の定義と条件
続いて「転載」の定義と、適切に転載を行うためのルールを見ていきましょう。
下記の3項目について解説します。
- 転載の定義
- 無断で転載できる著作物の例
- 違法な転載にならないための注意
詳しく見ていきましょう。
転載の定義
「転載」も引用と同じように、他者の著作物の全体または一部を自分の作品に取り入れる行為です。
引用の場合、他者の著作物は「自分の作品の従物」という位置付けであるのに対し、転載の場合は、1コンテンツ全体を見た時に、取り入れた他者の著作物が「自分の作品の主物」となっている状態です。
要は、その作品のメインとなっているのが引用した部分である場合には、それは「引用」ではなく「転載」になるということです。
これは自分にそのつもりがなくとも、客観的な判断で、他者の著作物が「主」となっていると認められるのであれば「転載」と言われてしまう可能性があります。
そのほか、引用に必然性がなく目的の正当性がないものだとすれば、それもまた「転載」です。
転載する場合の条件
適切に転載する場合の条件で、最も重要なのは「著作者の許諾が必要」ということです。
ここが引用と大きく違います。
それをふまえ、適切な転載の条件は下記4つです。
- 著作者の許諾があること
- 転載部分が明確に区別されていること
- 転載部分が改変されていないこと
- 出典が明記されていること
引用の条件を満たすことができずに、他者の著作物を自分の作品に取り入れようとするならば、必ず著作者の許諾を得るようにしましょう。
無断で転載できる著作物
転載には原則として著作者の許諾が必要ですが、著作権法では、下記2種類の著作物に限り許可なく転載できると定めています。
- 国や自治体が周知することを目的として作成した広報資料、統計資料、報告書
- 新聞や雑誌に掲載して発行された政治・経済・社会上の時事問題に関する論説
この2種類以外、要するに、世の中のほとんどの著作物は原則として無断転載できません。
自分のコンテンツに転載したい場合には、著作者の許諾を得ましょう。
よくある不適切な転載の例
著作者の許諾を得たからと、我が物顔で自分の作品に転載すると、これまた権利侵害になりかねません。
最重要の条件をクリアしたとはいえ、4つの条件のうちの残りの3つ、「転載部分を明確に区別すること」「転載部分を改変しないこと」「出典を明記すること」が守られていなければ、やはり著作権法違反です。
くわえて、著作者からの許諾を得る際に、転載にあたって上記以外のプラスアルファの条件を付けられたのであれば、それも守らねばなりません。
ちなみに、一般に公開しない、個人での利用の範疇での転載は違法ではありません。
たとえば、好きなキャッチコピーを集めた一覧のノートを友達に見せる、といった個人的な利用についてはこの限りではなくなります。
「出典」の定義と条件
「出典」とは、引用や転載の際に元となった著作物自体を指します。
引用・転載が行為を指すのに対し、出典は作品そのものを指します。
前述の通り、引用・転載のどちらにおいても出典を明記することは非常に重要です。
基本的な条件として、引用・転載部分のごく近くに、見る人にわかりやすく明記することとされています。
また、出典には、著作物の作品名や著作者の名前を記載しましょう。
著作物がWebページであれば、そのリンクを貼るのが最も分かりやすいでしょうし、書籍であれば正式な書名を一語一句間違えないよう注意しましょう。
まとめ|適切な引用は正義
今回は、「引用」「転載」「出典」の定義やそれぞれの違い、適切な方法、「著作権」などサイトの運営者として知っておくべき著作者の権利について解説しました。
最後に、適切な引用の表示例を挙げておきます。
適切な引用の表示例
著作権
著作権とは、著作物を作った人(著作権者)が持つ権利です。
写真であれば撮影者、イラストであれば制作者がおり、すべての画像は誰かの著作物であり著作権があります。
著作権は法律で保護されているため、著作権者の許可無しにブログに掲載・転載することは著作権の侵害にあたり不法行為となります。
出典:ブログに画像を貼る際の注意点まとめ | おゆきのBLab
このブログ内の「ブログに画像を貼る際の注意点まとめ」という記事の一部を引用した場合の例です。
WordPressには「引用」のブロックがあるので、取り入れる著作物を改変せず、必要な部分を枠内に記載し、引用部分以外と明確に区別しておくのがおすすめです。
また、出典がWebページなら、このようにリンクを貼っておきましょう。
適切な引用は正義です。
何を論じるにも根拠は求められます。
上手く引用を利用して、自サイトのコンテンツのエビデンス強化で質を高め、SEOにもより強いWebサイトを作っていきましょう。
以上、最後まで読んで頂きありがとうございました。
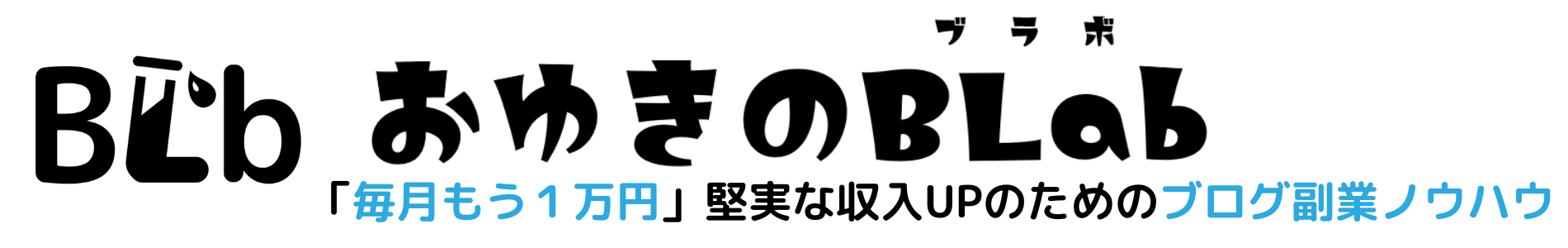
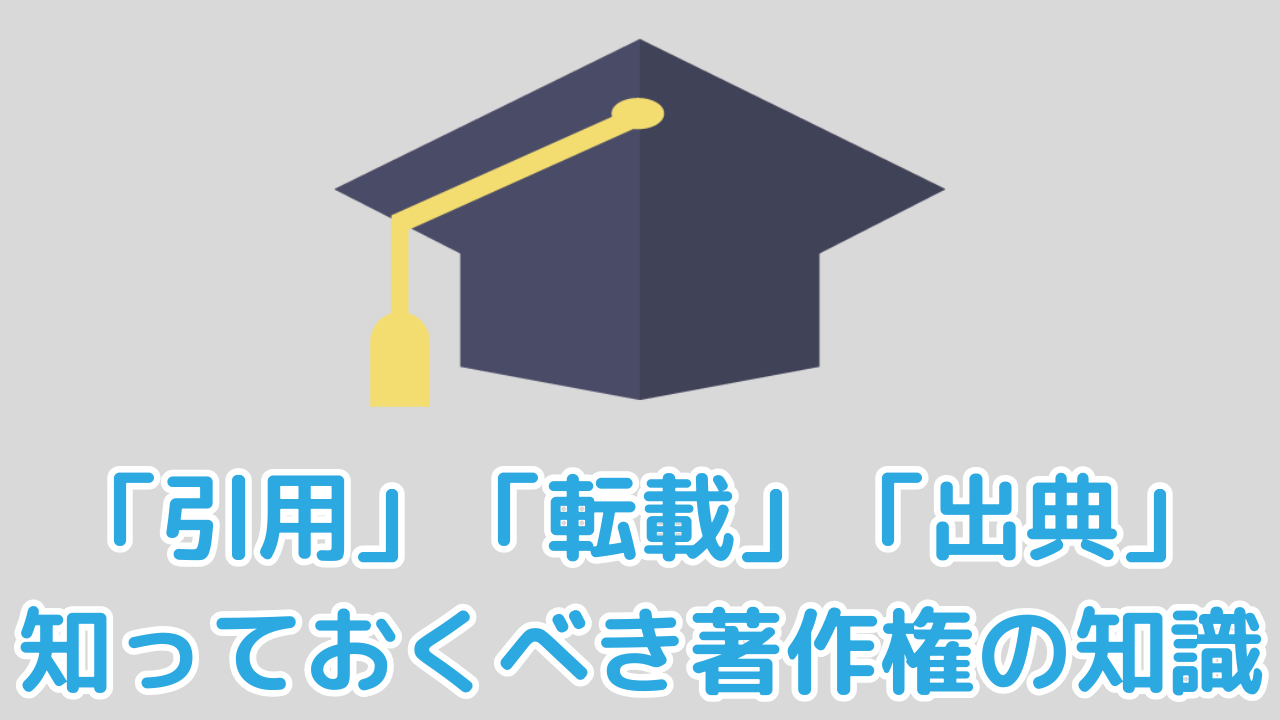



おゆきのBlabは、原則リンクフリーです。リンクを行う場合の運営者への許可や連絡は不要です。